古くて新しい奈良の酒~菩提酛(ぼだいもと)~
奈良と聞いて思い浮べるのは、大仏? 法隆寺? それとも鹿? 奈良漬や柿の葉寿司等の名物もありますが、菩提酛(ぼだいもと)を挙げた方は相当な酒ツウです。奈良の酒は、安土桃山時代にこの技法の酒造りで一世を風靡したのでした。

おすすめトレイル「鹿から酒へと続く道」
セミナーは中西康博さん(一般財団法人奈良の鹿愛護会 副会長)による鹿の現状の報告から始まりました。今、奈良公園は世界中から鹿を見に来る観光客で溢れており、歩いている人の9割以上が外国人という印象だそうです。皆が鹿せんべいを買って与えようとするため、午前中で売り切れてしまいクレームが相次いでいるのだとか。
奈良公園の鹿は飼育されていると思っている方も少なくないと思いますが、実は野生で、古くからこの地域では人と鹿が共生してきました。生息域は公園の周辺にある興福寺、春日大社、東大寺界隈です。都市化が進んでもこの共生関係が維持される文化は稀有、たいへん貴重です。この文化が国内外で広く知られるようになったことは喜ばしいことですが、観光客の急増は生育環境内のバランスを崩しかねず、観光振興と住民や鹿の生活をどう両立させるか試行錯誤が続けられています。

セミナーで薦めたのは、鹿や奈良公園周辺の名所にとどまらずディープな奈良を歩くトレイル(野山歩き)です。イントロは近鉄奈良駅から春日大社の山門を抜けて百毫寺(びゃくごうじ)までの約2km。この径を歩くだけでも奈良公園のにぎやかさとはまったく違う、古の万葉を体感できるといいます。そこからゴールの正暦寺(しょうりゃくじ)まではさらに12kmの行程です。帰りはJR帯解(おびとけ)駅まで5km歩くと総距離は約20km。これから梅雨入り前の気持ちのいい時期、あるいは秋のハイキングにピッタリでしょう。

ゴールの正暦寺は安土桃山時代に菩提酛という製法を確立した、日本酒の発祥の地のひとつです。
私が正暦寺を訪れたのは16年前の2009年でした。ちょうど興福寺創建1300年記念の年で、いい機会だと思い、酒の神様の総本山である大神神社(おおみわじんじゃ)に参拝して電車とタクシーで正暦寺へ、その後、興福寺で阿修羅像を拝観したのでした。帯解駅から正暦寺へのタクシーでは、運転手さんが「(正暦寺は)紅葉の頃はいいですよ。混まない早朝がお薦めです」と話していたことを覚えています。

菩提酛はかつての酒母の製法
菩提酛は日本酒のスターターである酒母(しゅぼ)の造り方のひとつです。酒を安全に造る(腐らせない)には、第一段階で糖分を食べてアルコールを出す酵母菌を増やし、第2段階で本発酵に進む手法が一般的です。
酒母(しゅぼ)づくりでは乳酸を活用します。米のでんぷんが糖分に変わるとさまざまな菌が集まってきます。この中に腐敗させる菌がいますが、乳酸菌を繁殖させ乳酸が出てくると悪さをする菌は生きていけません。一方で酵母菌は乳酸と相性がよく、乳酸菌に守られて活発に活動します。ですから酒母づくりで大事なのは、糖分が雑菌に汚染されないうちに乳酸を得ることになります。
菩提酛は生米を水に浸し乳酸発酵を誘導します。米を水に漬けるだけで乳酸ができるのですから不思議ですね。どうやってこの仕組みを発見したのでしょうか? 米を炊こうと水に漬けたまま放っておいたら水が酸っぱくなっていることに気づいたとしても、なぜその水を仕込みに使ってみようと思ったのかがわかりません。ただ、似た手法はかつて中国の黄酒(紹興酒など麦麹と米で造る酒)や沖縄の泡盛でも見られ、この時代に中国や東南アジアを行き来した僧侶がその技術を持ち帰ったのかもしれません。
正暦寺で造るからこそ「菩提酛」
講師の駒井さんが会長を務める「奈良県菩提酛による清酒製造研究会」は、この歴史に着目し、奈良県内の酒蔵に呼び掛けて菩提酛を復活させ、奈良酒に再びスポットを当てようと1996年に発足しました。
当初は15蔵が参加していましたが、現在のメンバーは7蔵です。発足から今日まで日本酒の消費量は減少を続け、販路は町のお酒屋さんからスーパーマーケットなど量販店に変わり、酒蔵は転廃業が相次ぎました。奈良県内に60軒あった酒蔵は30軒と半減しています。
研究会のメンバーもこの波に晒されました。今も参加している7つの蔵は、菩提酛による酒造りを復活させたことが独自の経営資源となり、ファンづくりに結びついているのではないでしょうか。
駒井さんたちの活動でユニークなのは正暦寺で菩提酛を造り、それをメンバーの酒蔵が自分の蔵に持ち帰って酒を仕込んでいる点です。菩提酛の製法を復元するだけならば、酒蔵が銘々に菩提酛を造ればいいように思いますが、正暦寺で酛を造ることにこだわり、1998年に正暦寺が酒母製造免許を取得し、1999年に500年ぶりに正暦寺で菩提酛を製造したのでした。
今、「菩提酛」と名乗れるのは基本的にこの研究会のメンバーの酒だけです(「御前酒」醸造元の辻本店(岡山県)はこれ以前から「菩提もと」を商品化しており例外)。近年は菩提酛と同様の手法で酒母を造る酒蔵がちらほら出ていますが、それらは「水酛(みずもと)」と呼ばれています。
甘口から辛口までさまざまな菩提酛の酒
最初の「百楽門(ひゃくらくもん)」と二番目の「菊司」は乳酸のニュアンスとドライな味わいが特徴で、料理との相性の幅が広く、食事をしながらゆっくり楽しめそう。
「菊司」は講師の駒井さんが造った酒で、駒井さんは「菩提酛の酒に限らず、食事をしながらおいしく飲める酒造りを目指しています」と繰り返していました。

その後、「つげのひむろ」、「三諸杉(みむろすぎ)」、「嬉(女偏に㐂)長(きちょう)」、「八咫烏(やたがらす)」、「鷹長(たかちょう)」と試して行きますが、進むごとに甘味とねっとり感が強くなり、「酒によってはまろやかさが際立ったり、濃厚で重量感が印象的だったりし、酒だけで楽しむか、食事に合わせるなら鰻のかば焼きや牛すき焼きのような甘味のあるしっかりした味の料理がよさそうだと思いました。

当初、「奈良県菩提酛による清酒製造研究会」はどの蔵もこの味わいに準じるよう取り決めていましたが、現在は造りをブラさなければ味わいの設計は蔵に任せることにし、今回試したように辛いものから甘いものまで幅があります。ただ、どれも乳酸由来と思われる香りや舌の脇を締めるような酸が共通していたように思います。
菩提酛の酒を試してみたい方は銀座の「奈良まほろば館」の「Cafe & Bar まほら」を訪ねてみてはいかがでしょうか。ここでは17時から19時の間は1500円で30分間、奈良県産の日本酒を自由に飲み比べできます。お酒のラインナップは随時変わるので、運がよければ菩提酛のお酒を複数飲み比べられます。
奈良まほろば館 :東京都港区新橋1丁目8-4 SMBC新橋ビル1F
※記事の情報は2025年5月8日時点のものです。
『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。
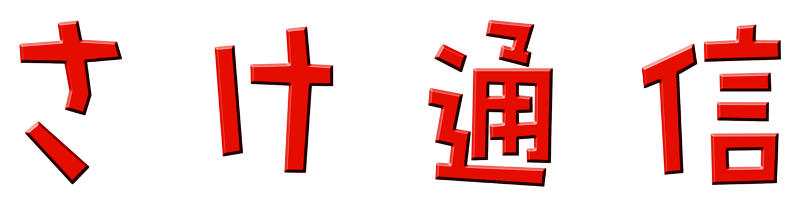
- 1現在のページ
 山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)
山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)