日本発の伝説のホップ「ソラチエース」使用のビールが全国で発売!
「ソラチエース」をご存知ですか? 日本で生まれたこのホップを100%使用した話題のビールが本格的に全国発売されます。

この銘柄の最大の特徴は、銘柄名にも冠されているホップ品種「ソラチエース」が使われていること。このホップの名前の由来は、北海道にある地名・空知であり、実際にそこで開発された。そして空知の由来は、「下る滝」を意味するアイヌ語の「ソーラップチ」だという。ホップは品種によってさまざまだが、小さな滝が階段状に連続するような形はほとんど共通している。そのホップが「下る滝」の地でも開発・栽培されているのは不思議な縁があると言える。
ソラチエースは、サッポロビールが1984年に空知郡上富良野町で開発するも、その「ヒノキやレモングラスのような香り」は、当時は個性的すぎて使われなかった。しかし品種として残すために米国に苗を持ち込み、やがて米国を中心とした世界中のクラフトビールのうねりの中で人気を博すようになった。そして近年ではこのホップを使った国産・輸入ビールが日本の消費者の手に届き始め、今年はこのSORACHI1984によってソラチエースの人気が格段に上がるかもしれない。
開発を担当した同社のクラフト事業部ブリューイングデザイナーの新井健司氏に、このホップとビールの魅力を聞いた。

ソラチエースをとにかく味わってもらいたかった
新井:ホップは古くから、苦味付けをする「ビターホップ」、昔ながらの爽やかな香りを付ける「アロマホップ」、アロマホップよりも香りと苦味が穏やかで上品な「ファインアロマホップ」に分類されてきました。しかし例えば1970年代に米国で、柑橘類の香りと苦味成分の多さを特徴とする品種が開発・発売されるなど、従来のアロマホップやファインアロマホップの枠では説明できない個性の強いホップが誕生していき、それらがフレーバーホップと呼ばれるようになりました。「ユニークアロマ(独特な香りの)ホップ」や、苦味成分が多くて苦味付けにも使えることに着目して「デュアルパーパス(二つの目的に使える)ホップ」という呼び方もあります。ソラチエースもヒノキやレモングラスといった独特の香りがありつつ、苦味成分が多いという特徴があり、フレーバーホップに含まれます。

ビール製造の立場から見る、ソラチエースの特徴を教えてください。
新井:多くのホップの香りは、ビールに使うとアロマ(ビールを口に含む前、グラスに鼻を近づけたときにする香り)で強く感じますが、ソラチエースは口に含んでから少しした後や、後味でその香りがよく出てきます。異なる品種のホップとうまく組み合わせて使えば、アロマと後味で異なる香りが出せるという、深みのあるビールをつくることができます。しかし今回は、ホップはソラチエースのみのシングルホップ(単一のホップ品種のみ使うこと)でつくりました。香り付けも苦味付けもこのホップだけでしたということであり、このホップの特徴がどんなものなのか、とにかく味わってもらいたかったからです。そのために、ソラチエースはアルコール度数が高い銘柄に使われることが少なくないようですが、今回の我々の銘柄は5.5%で、ボディーは特に強調していません。その分、このホップの特徴がきれいに出ていて、よく感じられるはずです。
今回使ったソラチエースは米国産と北海道の上富良野産を併用しているということで、それぞれ特徴の違いはあるのでしょうか。
新井:分析結果が上がってきているわけではないのですが、違うという印象を持っています。両方ともビールに使うと、ヒノキやレモングラスのような特徴はもちろん共通します。しかし大ざっぱに言えば、米国産は荒々しく、上富良野産はおとなしい感じです。上富良野産の収穫量はまだまだ少なく、全国の皆さんに味わってもらうには足りないので、米国産と併用することにしました。

多くの方にソラチエースの魅力を味わってもらうため価格は低めに
新井:まず3銘柄に共通するのは、ソラチエースのシングルホップだということです。そして①のときは、海外で有名だが日本ではほとんど知られていなかったソラチエースを、とにかく紹介したかった。実は、今回のSORACHI1984と、つくり方はほとんど同じです。非常に評判が良かったので、大きく変える必要がなかったからです。②ではさらに、国産ホップを盛り上げていきたいという思いがあり、上富良野産を100%使用しました。ソラチエースはサッポロビールが育種してきたことと、量はまだ全然取れないという希少性を一緒に訴えました。「国内にもこんなにすごいものがあるんだ」と知ってほしかったのです。350ml缶1本1125円という価格は決して安くありませんが、「それだけの価値があるんです」と自信を持って言えました。前にも述べた通り、上富良野産ソラチエースは特に繊細。だから②はピルスナーの製法を採用してホップ以外の特徴を極力下げて、ホップの特徴をより味わってもらうことを狙いました。①②を含めて、Innovative Brewerブランドで展開してきた銘柄のなかでは、「Nelson Sauvinの真髄」「絶妙のMosaic&Citra」「Polaris & Apolloの魔法」という、ホップを特徴として前面に出した銘柄の評判が特に良かったんです。そこで、Innovative Brewerブランドには従来は販売地域や経路で限定的な面があったところを、本格的な全国展開をする通年販売の銘柄として、ソラチエースというホップを特徴とするビールをつくろうとなったのです。
①は1本360円、②は1125円にしてきたなか、今回は270円(いずれも税込)と、かなり買いやすい価格になっていると思います。今回は①②と比べて文字通り桁違いの、22万ケース(350ml×24本換算)という販売計画によるスケールメリットがきいているからできたのでしょうか。
新井:今回も希少性を基にして、価格設定をもっと上げるという判断もあり得ました。しかし本当にしたいことは、なるべく多くの方にソラチエースの魅力を味わってもらうこと。スケールメリットももちろんありますが、この目的を達成するために、いろいろと努力をしました。
目下、ソラチエースを使った国内で入手できるビールとしては、常陸野ネストビールの「ニッポニア」や、2月から国内で通販が始まったブルックリンブルワリーの「SORACHI ACE」がありますが、「SORACHI1984」をつくるにあたって意識した点はありますか。
新井:もちろん両方飲んだことがあります。どちらも満足度が高く、良い気分にひたるのに素晴らしいと思いました。私たちの新製品は、前にも述べたように、ソラチエースの魅力を前面に出し、なるべく多くの方に味わってもらい、さらに「もう1杯おかわりしたい」と思ってもらえるような味わいを目指しました。価格帯も違いますので、競合としては見ておらず、むしろこの素晴らしいホップを一緒に盛り上げられればと思っています。
「SORACHI1984」からのミッションを遂行してもらう「ミッションアンバサダー」を1984名募集しましたね。ビール会社が公募して任命するこの規模のアンバサダー企画は、少なくとも日本では初めてではないでしょうか。この企画を実施した経緯と効果について教えてください。
新井:SORACH1984を広めるに当たって「ブランドブック」という冊子もつくったように、誰かに話したくなるストーリーを丁寧に伝えることを重視しました。ストーリーブックを見ながら飲めば、誰かに話したいことがたくさん見つかるでしょう。それを発信してもらう場としてはSNS(交流サイト)が良いと判断して、アンバサダー企画を採用し、採用者に製品2本とブランドブックをお送りし、飲んだ感想をSNSで発信してもらいました。製品名の一部であり、ソラチエースが生まれた1984年にちなんで、1984名を募集したところ、なんと1万名超もの応募がありました。皆さんがお書きになったアンバサダーへの意気込みは、社員が本当にすべて目を通して、1984名を選びました。SNSで流れてくる投稿を眺めていると「ビール好きはみんな任命されている」と思うかもしれませんが、きちんと審査しましたので、当たり前のことかもしれません。面白かったのは、1984年生まれの方や、空知郡に縁がある方が反応してくれたことです。またアンバサダーの方々の投稿は、「当たった、うれしい」とか「おいしい」といった単純なものではなく、長く書かれたものが多いですね。ブランドブックが製品に関する情報の引用元になりますし、それに共感してくれた方が多かったのではと感じています。これまでにない試みとしては、業務用の樽の販売をすることです。従来、Innovative Brewerの銘柄の樽は、サッポロビール系レストランチェーンの銀座ライオンで飲めることはありましたが、それ以外にも卸すのは今回が初めてです。これまでも「卸してくれないか」と引き合いが多く、外飲みでもぜひにぎやかに味わってもらいたいと思っています。

●●●
「SORACHI1984」の特徴をよく味わうために、他のソラチエース使用銘柄と並べて飲んでみた。左から「SORACHI1984」、昨年サッポロが限定発売してちょうど2019年4月が賞味期限だった「伝説のホップ ソラチエース」、常陸野ネストビール「ニッポニア」「ニッポニアピルスナー」、ブルックリンブルワリー「SORACHI ACE」だ。2019年4月現在、「伝説のホップ ソラチエース」を除いて、小売店かネット通販で買うことができた。
まず大まかな傾向としては、サッポロの2銘柄と常陸野ネスト・ブルックリンの3銘柄で違いがある。前者はソラチエースのヒノキやレモンのような香りが際立っていてすっきりしているのに対し、後者では麦芽の甘味を想起させる香りや他のフルーティーな香りと調和していて、全体としては濃厚だ。
「SORACHI1984」と「伝説のホップ ソラチエース」を比べると、前者はまずヒノキのような上立ち香(アロマ)がある。口に含むとすっきりとしているが甘味もあり、甘味と高まり合うオレンジのような香りも感じられる。しっかりとした苦味が感じられて、まるでマーマレードのような味わいだ。後者は前者よりもすっきりしていて、よりヒノキらしさが感じられ、その次にレモンのような味わいがある。どちらもなるべく静かに、泡を立てずに注いで、口の中で弾けるホップの味わいを楽しんだ。
税区分の「ビール」に、世界で尊敬されている日本発の材料を用いて、味わいの個性も強く、しかしながら買いやすい価格の通年銘柄が登場した。日本のビール市場の健全な発展は、この銘柄が定着するかどうかにかかっていると言っても過言ではないと思う。

- 1現在のページ
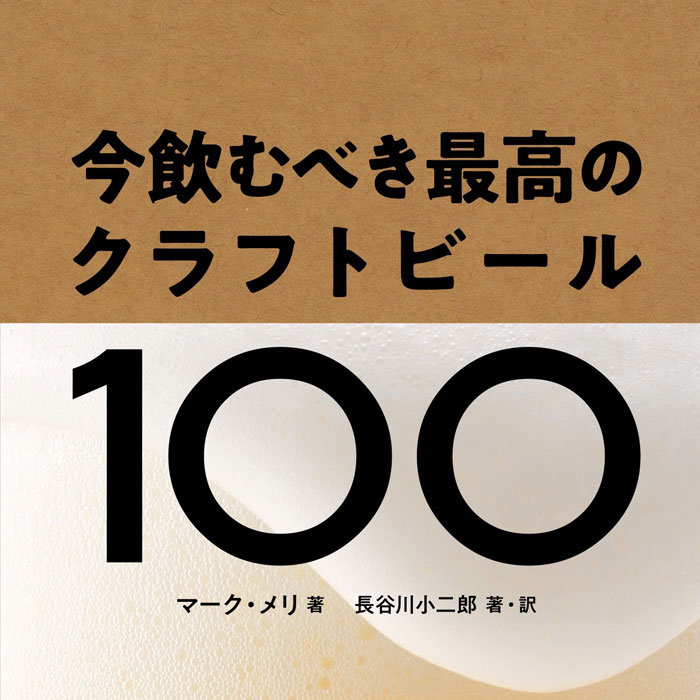 長谷川小二郎
長谷川小二郎